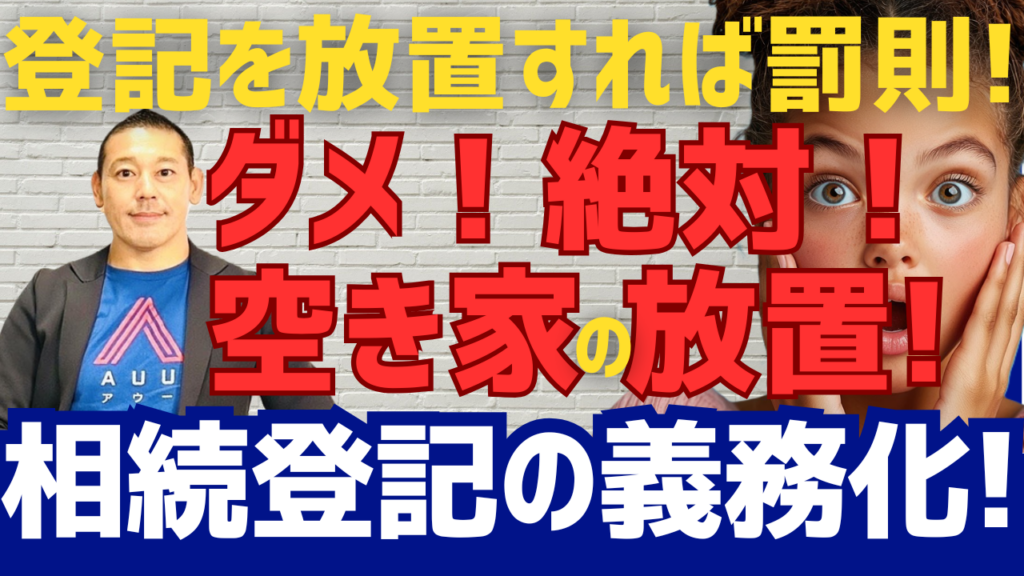
2025年、日本は「空き家900万戸時代」に突入しました。これは全住宅の13.8%に相当し、過去最多の水準です。
そんな中、空き家に関して登記をしなかっただけで“過料”が科される時代がやってきています。
背景には、空き家が増えるだけでなく、誰のものか分からない“所有者不明土地”の急増という、より根深い問題があります。
国はその対策として、2024年から「相続登記の義務化」を本格化。2026年には住所変更登記の義務化も控えており、空き家問題は今、まさに“法の力”で動き出しています。
■ 登記しなかっただけで、罰則対象に?
これまでは、親の家を相続しても「名義変更しない=問題なし」という風潮が一般的でした。
しかし、2024年4月の法改正(不動産登記法・民法)によって、その常識は大きく変わりました。
| 義務化された項目 | 内容 |
|---|---|
| 相続登記の義務化 | 相続を知った日から3年以内に登記しないと、過料(最大10万円) |
| 住所・氏名変更の義務化 | 所有者の住所や氏名が変わったら2年以内に登記(2026年施行予定) |
📌 つまり、相続や住所変更があったら「登記をしない=違法」になる時代へ。
■ 空き家が生まれる4つの“ありがちなパターン”
空き家になるケースは、決して特別なものではありません。
誰にでも起こりうる、ごく身近な「生活の延長線上」にあります。
① 親が亡くなり、実家を相続したが、結論が出ないまま放置
相続人が兄弟で意見が合わず、名義は親のまま。管理はされず、固定資産税だけが発生。
🔧 対策: 相続時に話し合いと登記をセットで実行。第三者の仲介も有効。
② 親が施設に入り、家が空き家化。判断が先延ばしに
「一時的な空き家」と思っていたら数年が経過。劣化が進み近隣からの苦情も。
🔧 対策: 利用見込みがないなら、早期に売却・活用の選択肢を検討。
成年後見制度や家族信託で法的な名義整理も。
③ 地方に不動産を持っているが、需要がなく諦めムード
「売れない」と思い込んで放置。草木が伸び、将来的には“管理不全空き家”に指定されるおそれも。
🔧 対策: 自治体の空き家バンクや、民間のマッチングサービスを活用。
DIY型賃貸やAI査定など新たな選択肢が広がっている。
④ 共有名義(兄弟・親族間)で話がまとまらず、動けない
名義人が複数いて、全員の同意が取れず放置。数十年後、相続人がさらに分散し、収拾がつかなくなる。
🔧 対策: 新制度により、過半数の同意で処分可能に。
専門家のサポートでスムーズな手続きが進められる。
■ 「管理しない」では済まされない時代へ
登記をしないまま放置していると、家は“管理不全空き家”に指定されるリスクがあります。
これは、2024年の「空き家対策特別措置法」改正で新設された区分で、該当すると固定資産税の優遇が解除され、税負担が最大6倍に跳ね上がることも。
さらに、自治体からの是正指導、命令、場合によっては代執行(強制撤去)に発展する可能性もあります。
■ 空き家を“負の遺産”にしない─活用という選択肢
空き家は放置すればリスクになりますが、逆に言えば地域の未来を支える“資源”にもなり得ます。
▷ 徳島県三好市
空き家を若者向け移住住宅に活用。就業支援も含めて地域活性化につなげる。
▷ 長野県飯田市
DIY可能な空き家バンクを展開し、若年層の移住・定住を促進。
▷ 東京都豊島区
AIによる空き家予測や所有者特定技術を導入し、迅速なマッチングを実現。
こうした事例に共通しているのは、「空き家をきちんと登記し、誰が所有しているかを明確にすること」から全てが始まっている点です。
■ 登記は「責任」ではなく「選択肢」を広げる第一歩
空き家問題は、もはや一部の人の話ではありません。
高齢化・人口減少が進む日本では、誰もが“空き家の当事者”になる可能性があります。
しかし、正しいタイミングで登記を行い、行動を起こせば、
それは「負担」ではなく、「未来を動かす選択」になります。
■ 空き家をお持ちの方、登記がまだの方へ
空き家や相続登記に関して、
「何から手をつければいいのか分からない」
「専門家に相談するタイミングがわからない」
と感じている方は少なくありません。
AUUでは、こうしたお悩みに対して状況に応じた個別サポートを行い、必要に応じて専門家へお繋ぎしています。
空き家を“負の遺産”にしないために。
“登記する”という行動が、あなたと地域の未来を守る第一歩です。
AUUにご相談の上、専門家をお繋ぎさせて頂く事も可能です。
お気軽にお問合せ下さいませ。
記事による意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要があります。記事の内容を実行される場合には、専門科等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本記事をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。
タグ:AUU





